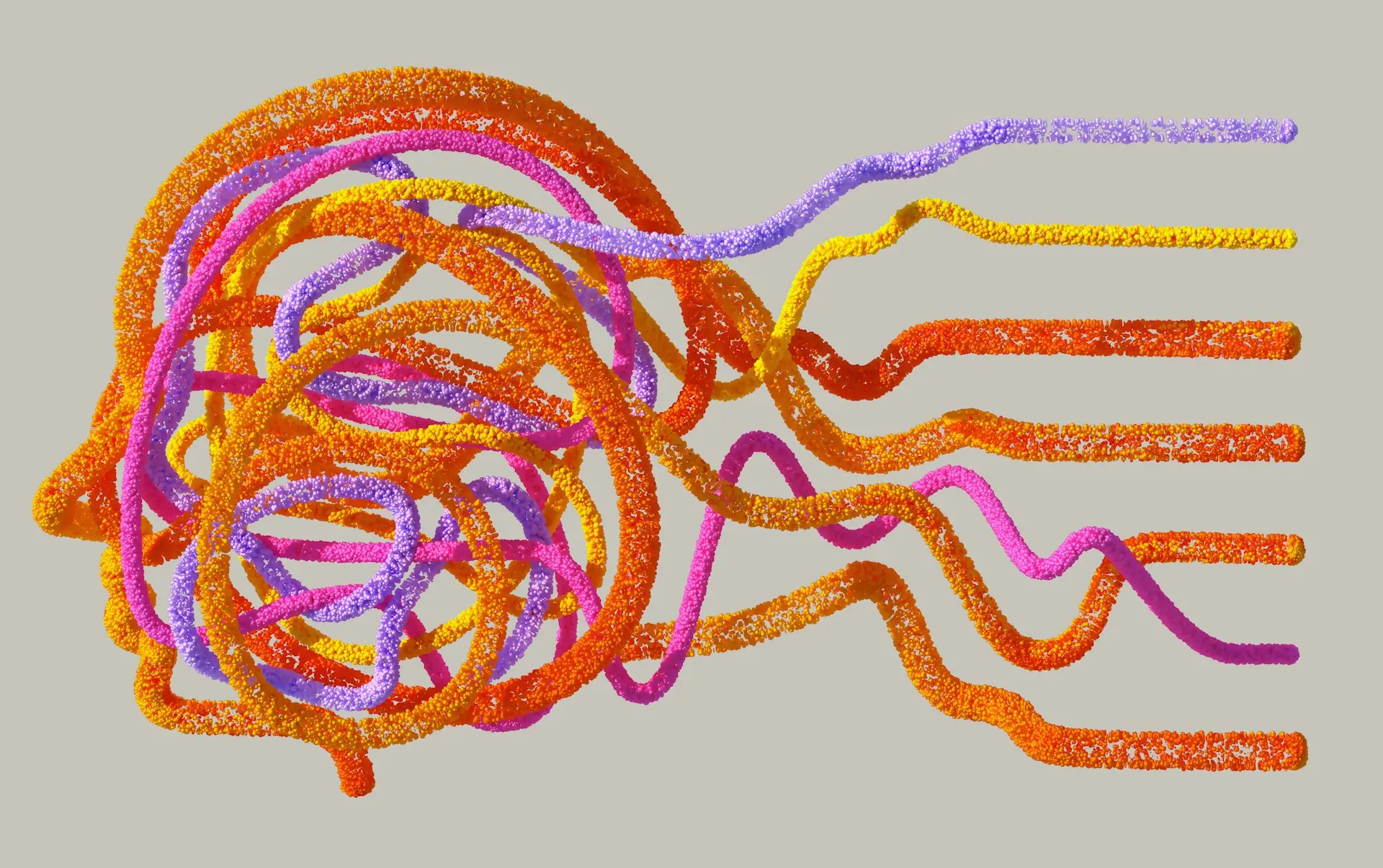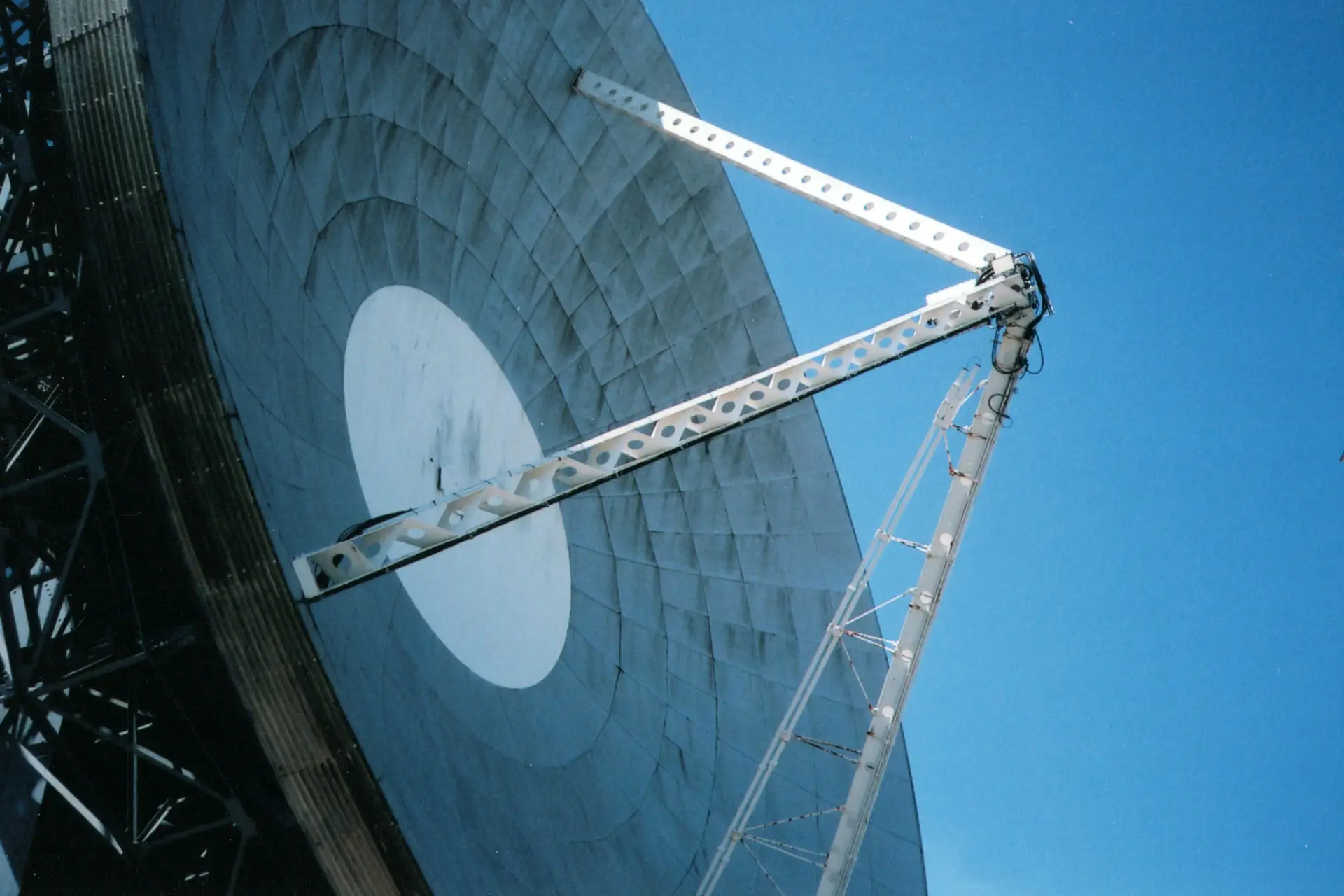EV電池リサイクル企業のRedwood Materialsは、シリーズEで3億5000万ドルの資金調達を発表
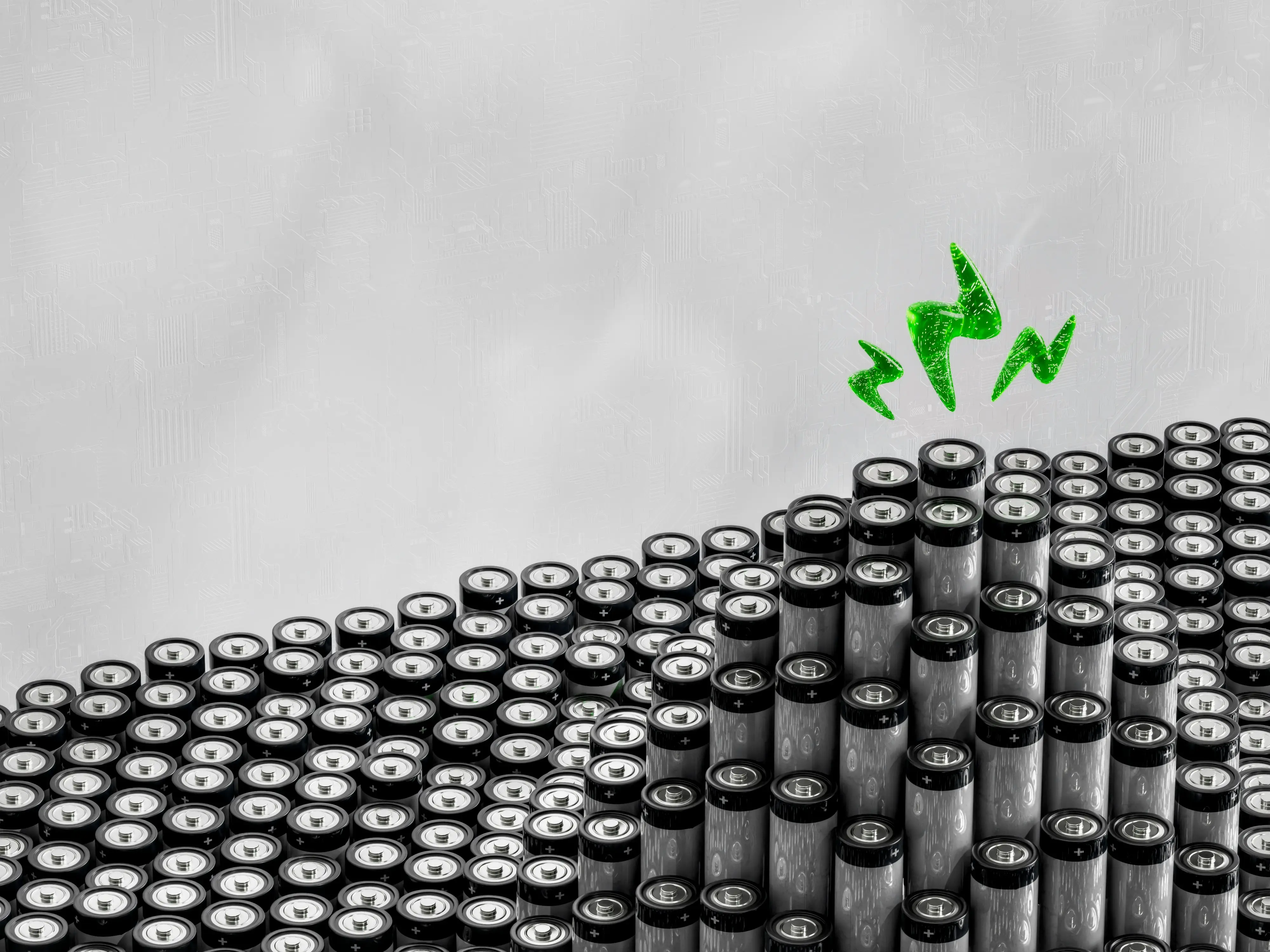
Redwood Materialsは、2017年にTesla, Inc.の元CTOであるJB Straubel氏が創業した米国の企業である。リチウムイオン電池のリサイクルを起点に、コバルト・ニッケル・銅・リチウムといった重要素材の精製と、これらを活用した次世代グリッド級エネルギー貯蔵システム(BESS:バッテリー・エネルギー・ストレージ・システム)を提供している。EV廃電池の“セカンドライフ”利用にも注力し、AI/データセンター向け電力需要の高まりに応じたインフラ構築を進めている。
2025年10月、同社はシリーズ Eラウンドとして約3億5,000万ドルの資金調達を完了した。ラウンドはEclipse Venturesが主導し、NVIDIA Corporationのベンチャー部門NVenturesをはじめとする戦略的投資家が参加している。調達資金は、電池素材の精製・生産能力拡大およびグリッド級エネルギー貯蔵システムの展開加速、エンジニアリング/オペレーション人材の強化に充てられる。
現代のエネルギー転換期においては、リチウムイオン電池の需要急増に対し、原料採掘と廃棄の両面で環境・供給リスクが高まっている。新規採掘に依存する供給網は不安定で、コバルトやニッケルなどの精製過程では高い環境負荷が発生する。これにより、電動化社会を支える電池産業の持続性が脅かされ、再生可能エネルギーの普及やグリッド安定化を阻む要因となっている。
同社は、廃電池の回収・再生から新規素材生産までを一体化した“クローズドループ型バッテリーサプライチェーン”を構築し、この課題を解決している。リチウム、ニッケル、コバルト、銅などを再精製し、カソード活物質や銅フォイルを再製造。これにより、環境負荷を大幅に削減しつつ、池素材の国内生産とエネルギー自立を両立させる持続的なエネルギー基盤を形成している。
以前、弊社記事必要に迫られるリチウムイオン電池リサイクルの技術開発においても指摘したとおり、電動化の進展に伴い電池の再資源化と供給網の循環化は世界的な課題となっている。Redwood Materialsの取り組みは、まさにその潮流を体現するものであり、再生素材を起点としたエネルギーインフラの再構築という点で、産業全体のモデルケースといえる。
エネルギー貯蔵と素材再生を結ぶ垂直統合モデル
同社のエネルギー部門「Redwood Energy」では、大規模エネルギー貯蔵システムを低コストで設計・統合・導入している。国内調達の新品・再利用バッテリを組み合わせ、輸入関税を回避しながらスケーラブルな構成とする。制御プラットフォーム「Pack Manager」によって、どのバッテリパックも一元的に安全・効率的に運用できるよう設計されている。
このシステムは、電力グリッドのピークシフト/需要応答、AI/データセンター向け高速電力供給、停電時バックアップなど多用途に対応しており、長時間運用を前提とした「継続供給性能(duration advantage)」を重視している。容量の拡張に制限がなく、用途やスケールを問わず導入可能なアーキテクチャを特徴とする。
材料部門では、リチウムイオン電池から廃棄・使用済みバッテリを年間20 GWh超回収し、リチウム・ニッケル・コバルト・銅などの重要素材を95%以上の回収率で精製・再生する。これにより、米国に長らくなかった商業規模のニッケル・リチウム・コバルト製造拠点を構築し、国内の電池素材供給体制の強化に寄与している。
宇宙をインフラに変える実証フェーズの始動
今回の資金調達により、同社はエネルギー貯蔵システムの展開と素材精製・生産能力の強化を加速する。特に、AIデータセンターや産業用大規模グリッド向けに、低コスト・大容量・国内製造のバッテリー技術を提供するため、エンジニアリング・オペレーション体制を拡充する計画である。
さらに、同社は米国内におけるクリティカルマテリアル(リチウム、ニッケル、コバルト、銅等)と電池素材の垂直統合サプライチェーンの構築を目指している。海外依存を低減し、再生可能エネルギーの不安定性やAIインフラの電力需要という課題に対し、持続可能で強靱な電池基盤を確立することで、米国のエネルギー独立や電動化推進に貢献する所存である。
参考文献:
※1:Redwood accelerates energy storage, announces $350 million Series E funding( リンク)
※2:同社HP( リンク)
【世界のEV・電池の技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】
世界のEV・電池の技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。
先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら
CONTACT
お問い合わせ・ご相談はこちら