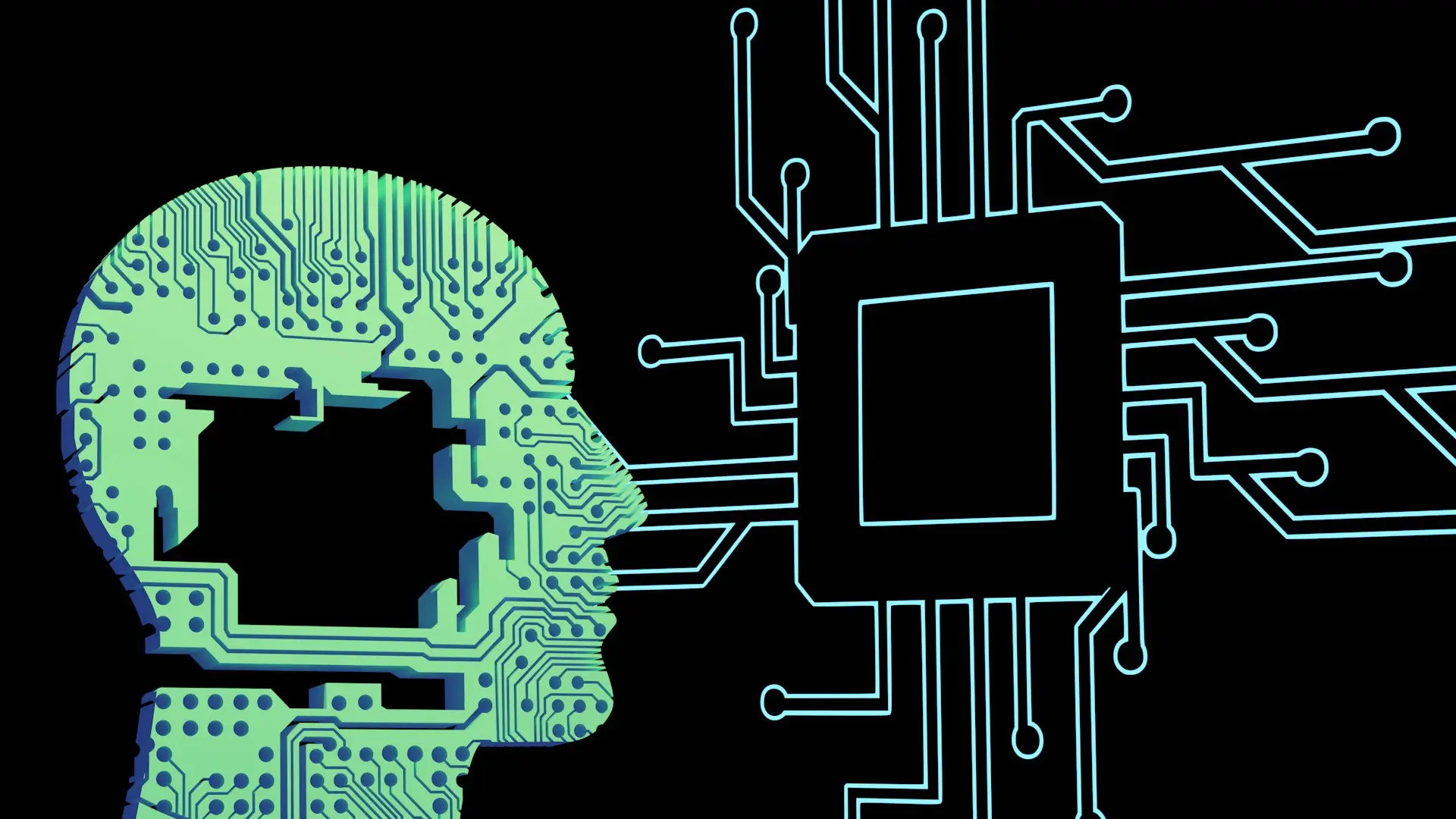医療データ管理プラットフォームを開発する米Predocが、3,000万ドルの資金調達を発表

米国のヘルスケアAIスタートアップのPredocが、2025年9月2日に、シリーズAを含む資金調達で3,000万ドルを獲得した。同社は医療業界で日常的に発生する “ドキュメントチェイシング(患者情報を紙やファックスなどで収集する作業)” を、AIによって自動化し、記録の取得から分析までを効率化するサービスを開発している。
今回の資金調達は、Base10 Partners がリードし、Northzone、ENIAC Ventures、ERA Ventures が参加している。また、Flatiron Health、Datavant、Thirty Madison、Blackstone といったエンジェル投資家も資金を提供した。
米国における医療情報管理の効率化に挑む
米国の医療現場では、依然として患者情報の多くが紙やFAXでやり取りされ、必要な情報を集めるのに時間と労力を要している。(こうした課題は日本の医療現場においても大きな課題として存在している)
Predocは2022年に米国で設立されたスタートアップであり、同社はこの非効率を解消するためにAIを活用し、医療記録の取得から整理、分析までを自動化する仕組みを提供している。これにより、従来は数週間を要していた記録収集を数分から数日で完了できるようにしている。また、同社はAIに対して、医師の判断を置き換えるものではなく補強する役割を担い、医療従事者が本来のケアに専念できる環境を支えるツールだと考えている。
AIを活用し、患者情報の収集・構造化・解析を効率化
同社はAIを用いた患者情報の自動収集・構造化・解析を強みとしている。
診療記録や検査結果、薬歴に加え、PDFやFAX、スキャン画像といった非構造化データまでを一括して取得し、AIによる文字認識や抽出で整理・統合する。従来は医師やスタッフが多大な時間をかけて探していた情報を、短時間で活用できる点が特徴である。
さらに、臨床試験の適格性チェックや患者履歴の要約など、具体的な問いに応じた出力を生成できる点も特徴である。AIが生成した結果は「Human-in-the-loop」により専門家が確認し、信頼性を高めている。
また、セキュリティとプライバシーは設計段階から組み込まれており、HIPAA準拠の暗号化やアクセス制御に対応する。Predoc自体が患者データを恒久的に保持することはなく、必要な処理を施したうえで医療機関に返却する仕組みとなっている。あくまで「データの所有権は医療機関と患者にある」ことを前提に設計されている。
HIM(医療情報管理)未開拓市場90%を狙う
PredocのCEO Nishant Hari氏は「われわれは医師を置き換えるのではなく、臨床判断を補強し意思決定を早めることに価値がある」と述べ、今後もHIM(医療情報管理)の自動化を加速し、院内の記録取得チームを置き換える完全アウトソース型ソリューションとして展開を拡大する方針を示した。
共同創業者のKulkarni医師も「診断は医師が最もやりたい仕事であり、技術の役割は診断前後の煩雑な事務負担を取り除くことだ」と語り、医師が診療に集中できる未来を目指している。
今回の投資のリードであるBase10 Partnersは、「大手HIMプロバイダーが対応しているのは市場上位10%に過ぎない。Predocのアプローチは残り90%の医療機関にもソリューションを提供できる」と述べ、同社の成長余地の大きさを指摘している。
参考文献:
※1:Predoc raises $30 million to stop document chasing in healthcare( リンク)
※2:同社公式HP(リンク)
【世界のデジタルヘルスケアの技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】
世界のデジタルヘルスケアの技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。
先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら
CONTACT
お問い合わせ・ご相談はこちら