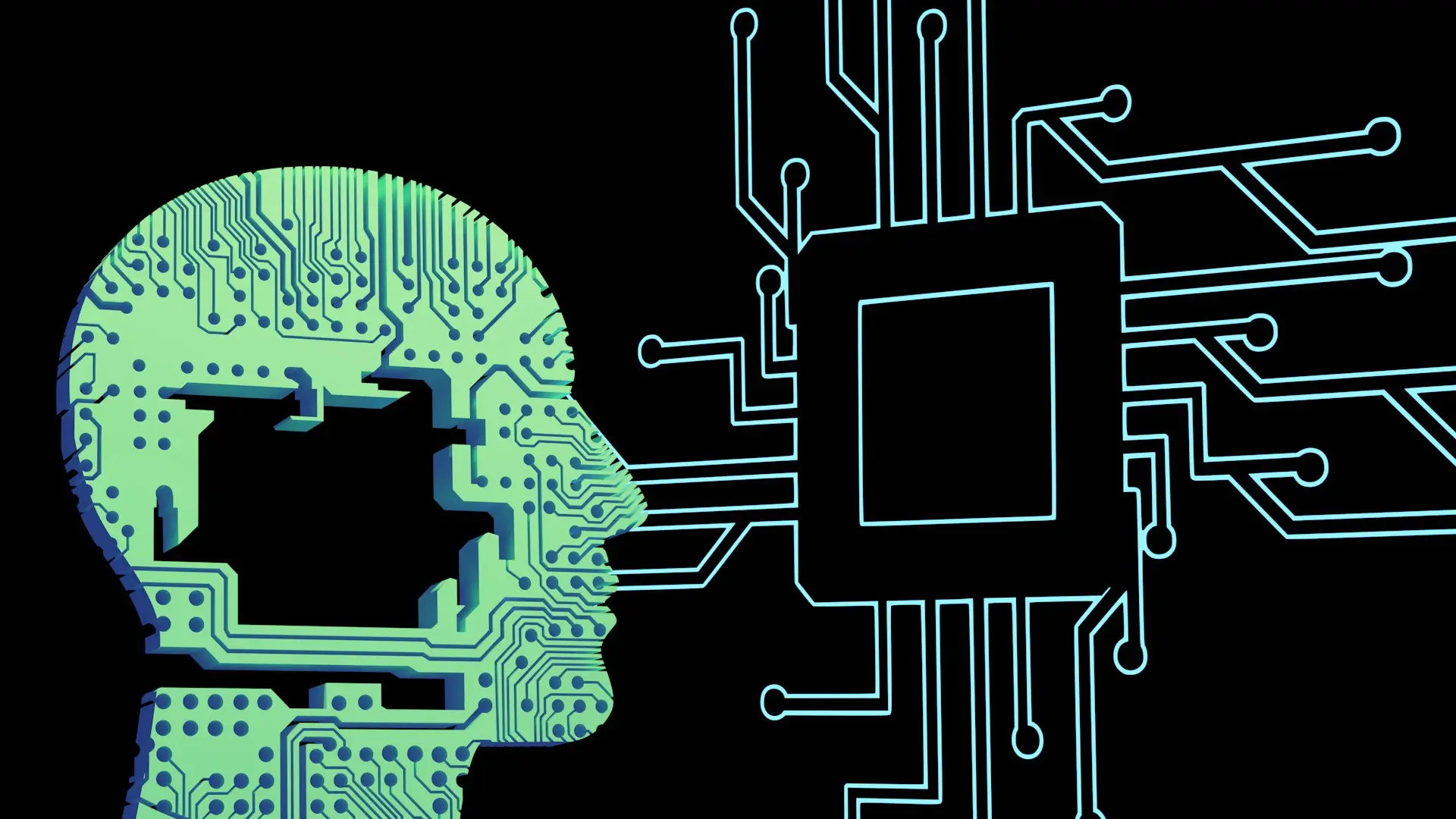Samsung「C-Lab」のプログラム内容と生み出した成果。他社の類似事例も紹介

大手製造業各社は、市場環境の変化に対応したプロダクトを生み出し続けるため、社内にイノベーションハブを設ける、社内企業プログラムを行うといった取り組みをする例が見られる。
こうした中で、Samsungが社内外からアイデアを募る「C-Lab」は、米国で開催される展示会「CES」で毎年、成果が披露されるなど、注目を集めるプログラムといえよう。本稿では、C-Labについて取り上げる。
Samsung ResearchとC-Labの概要
C-Labは、SamsungのR&D部門であるSamsung Research内で行われるプログラムである。まず、Samsung Researchについて、さらにC-Labについて、概要を取り上げる。
Samsung Research
Samsung Researchは、韓国・ソウルのSamsung Seoul R&D Campus内に、ヘッドクォーター的な拠点を有するSamsungのR&D部門である。
韓国以外にも、欧・米・アジアの14カ国に拠点を展開。日本にもSamsung R&D Institute Japanという組織があり、横浜と大阪の2拠点体制となっている。こちらは、1992年にSamsungが設立したアイテックという企業が前身で、1998年に「サムスン横浜研究所」に、2013年に「サムスン日本研究所」に商号変更した。
各国のSamsung Researchのウェブサイトを読むと、それぞれで研究分野に微妙な違いがあることが見て取れる。韓国、米国、日本のSamsung Researchが研究する分野を表にした。丸印が付いている項目が、当該研究拠点で取り組んでいるテーマだ。
| Samsung Research(韓国) | Samsung Research America(米国) | Samsung R&D Institute Japan(日本) |
AI | ● | ● |
|
データインテリジェンス | ● |
|
|
ロボット工学 | ● |
| ● |
次世代デジタル家電 | ● |
|
|
次世代通信 | ● | ● |
|
モバイルプラットフォームとソリューション |
| ● | ● |
モバイルプロセッサ |
| ● |
|
次世代ディスプレイとメディア | ● | ● | ● |
Tizen | ● |
|
|
SoCアーキテクチャー | ● |
|
|
セキュリティーとプライバシー | ● |
|
|
ソフトウェアエンジニアリング | ● |
|
|
デジタルヘルス |
| ● |
|
生活家電 |
|
| ● |
編集部制作
なお、TizenはSamsungやLinuxなどが開発したスマートフォンOSである。
C-Lab
C-Labは2012年設立。従業員のアイデアを事業に結びつけるためのプログラムである。C-Labとは、「クリエイティブラボ」の略だ。
C-Labには社内からアイデアを募集するC-Lab Insideとスタートアップとのオープンインベーションを狙ったC-Lab Outsideがある。
まず、C-Lab Insideについて。アイデアのある従業員は、オンラインプラットフォームを通じて応募。審査に通過すると、シード資金が支給され、それまで従事していた業務から離れてプロジェクトに専念する。社内からメンバーを集めることも可能だ。
Samsungの社員であれば、役職、職歴に関係なく、全員がC-Lab Insideに応募できる。2020年頃の情報であるが、アイデアが審査通過するためには1000倍もの倍率がある中を潜り抜けなければならないという。
一方、C-Lab Outsideは選考で書類審査や面接などがある点は、他のアクセラレーションプログラムと同じ。通過すると、最大₩100m(約1000万円)が支給され、Samsungのオフィスを1年間利用できる権利などの支援が受けられる。オフィスは、ソウル、大邱、光州、慶北の4カ所にある。
C-Labがもたらす3つの効果
C-Labによって得られる効果を、詳細に見ていきたい。「社内外双方からのイノベーション創出」「社内のチャレンジ精神・心理的安全性の醸成」「事業創出による個人と社会にとっての利益」という3点を取り上げる。
社内外双方からのイノベーション創出
SamsungがC-Labに取り組む最も大きな目的は、イノベーションの創出であることに異論はないだろう。C-Lab Insideでは、社内のリソースを生かし、従業員のイノベーション意識や当事者意識を醸成する効果がある。一方、C-Lab Outsideは社外とSamsungによるイノベーション、すなわちオープンイノベーションを促すものとなる。
若い世代にとってはSamsungというと、モバイルのイメージが強いかもしれない。一方、それより上の世代にとっては家電というイメージもあるだろう。前述のようにSamsung Researchでは、そうしたプロダクトだけでなく、AIやロボティクス、ヘルスケアなど、エレクトロニクスと関わる多様な研究が行われている。
そのため、応募者や創出する事業も多様となる。よって、さまざまな領域でのイノベーション創出につながる。
社内のチャレンジ精神・心理的安全性の醸成
これはC-Lab Insideに当てはまる話だが、Samsung従業員のチャレンジ精神を育む、心理的安全性を醸成する効果が挙げられる。
企業規模が大きくなれば、人材も含めあらゆる面が保守的になり、全体的に失敗を恐れる文化となりやすい。これは、国を問わず見られる傾向といえよう。
しかし、企業としてチャレンジを後押しすることで、失敗を遠ざけるのではなく失敗から学ぶ文化を醸成する。現代的な言葉にすれば、心理的安全性を醸成する効果ともいえそうだ。
また、C-Labのプロジェクトは原則的に1年間となっており、C-Lab Insideの場合、事業化の目処が立たなければ従業員はSamsungの事業に戻る。しかし、プロジェクトに専念した経験は社内の事業にも生かされるし、あらためて別の新規事業創出があれば、貴重な人材ともなり得るだろう。
事業創出による個人と社会にとっての利益
C-Labに持ち込まれるアイデアは、社会課題解決を目指すものも少なくない。事業化に結び付けば、ソリューションとなり、社会にとっての利益ともなる。
過去、C-Lab InsideからWELTというプロダクトが生まれた際には、そのための企業がSamsungよりスピンオフした。創業者兼CEOのSean Kang氏は、Samsungのヘルスケア部門で当時、唯一の医師免許保有者だった。そうした貴重な人材を社内に温存することなく、活躍できる場に送り出したということになる。社内起業家の視点に移せば、擬似的な社内起業ではなくリアルな起業の経験に結び付く。
C-Lab Outsideの応募企業にとっては、グローバル企業からの資金とナレッジを享受できるチャンスとなる。また、C-Lab InsideにしてもC-Lab Outsideにしても、事業が成功すればSamsungのブランド力を向上させる要因ともなるだろう。
CES 2025に見るC-Labの現在
C-Labから生まれたアイデア、C-Lab Outsideに選ばれた企業は、毎年のCESで披露される。最新のCES 2025から、C-Lab Outsideに選定された企業を取り上げる。
ENERZAi
SamsungはENERZAiを「次世代AI推論最適化エンジン」の開発企業と位置付ける。
ENERZAiのウェブサイトを読むと、特に映像や画像をAIにより解析することに強みを持つようだ。たとえば、監視カメラの映像から霧や黄砂などの阻害要因を除去し、事故・事件発生時の原因究明などに役立てる。
また、車に関するソリューションとしてもAIを活用しており、レーダーとの併用で子どもの置き去りを検知する、シートベルトが外れているのを乗員に知らせる、などの用途を提案している。
ENERZAiの企業紹介動画
LabSD
LabSDは、デジタル検眼鏡を開発する。検眼鏡のレンズなどがある部分と中古スマートフォンを組み合わせ、できる限りコストを削減。眼の内部の映像は、スマートフォンの画面に映し出される。
このプロダクトにより、失明や非感染性眼疾患の予防を目指す。
LabSDのプロダクト紹介動画
Quester
Questerはハンドトラッキンググローブを開発する企業。人間の手の動きをトラッキングし、ロボットの動作に生かすためのものだ。
活用領域として想定するのは、外科手術の訓練、航空機の操縦や整備の訓練、リハビリなどを挙げる。これら分野の熟練者の動きをトラッキングし、シミュレーターなどをつくることにも役立てるという。
C-Labと似た他社の制度
Samsung以外の企業で、C-Labと同様のプログラムを取り上げる。スウェーデンのEricssonとドイツのBoschの事例だ。
Ericsson ONE
スウェーデンの通信機器メーカーであるEricssonは、Ericsson ONEというプログラムを設けている。C-Lab Insideと同様、社内企業を促すものだ。
プロセスは、社内からの提案の中から審査チームがステップアップできそうなアイデアを選定。プロトタイプの製作、テスト、検証を行っていき、実用最小限の製品(MVP)をつくる。計画通りに進めば、事業化する流れだ。
2023年の段階では、Ericsson ONEによってEricsson Digital Human(EDH)というホログラム通話の開発が行われていた。EDHは現在、ソフトウエア開発者用キットを頒布していることが確認できる。
Bosch Business Innovations
Boschは2012年より、チームを組成しての新規事業開拓をスタート。2019年には、grow platformという法人を立ち上げ、それまで点在していたイノベーションハブを統合した。
そして2025年、grow platformはBosch Business Innovationsへと改組している。
社内からイノベーションを起こすことを目指すBosch Business Innovationsで特徴的なのが、シード、グロース、スケールといった段階に分け、それぞれに適した投資を行ったり社内起業家に専門プログラムを提供していたりする点。同社は2019年以降、平均収益成長率が64パーセントを記録しているという。
つまり、アイデアの事業化への後押しとともに、投資効率を最適化する仕組みも構築している。
まとめ|必要とされる支援は技術以外にもある
製造業が社内イノベーションを起こす場合、既存のアセットを元に市場から受け入れられるようプロダクトをブラッシュアップしていくことが不可欠だ。一方、技術面だけでなくマーケティング面の支援を行えば、さらなるオープンイノベーションや事業スピードの加速につながる。
この点でC-Labは、毎年のCESへの出展でプロダクト、ソリューションを周知する。また、表に出ないだけで、グローバルに展開するSamsungならではの有形無形のリソースが使われている場合もあるだろう。社内起業家やスタートアップが持ち合わせない、技術以外の支援もイノベーションには必要であるのだ。
参考文献:
※1:Samsung Research(リンク)
※2:Samsung R&D Institute Japan(リンク)
※3:Samsung Research America(リンク)
※4:Samsung C-Lab(リンク)
※5:A rare look inside Samsung's secretive ideas lab, Kristie Lu Stout他, CNN(リンク)
※6:優秀な社員を外に放つ、サムスン「C-Lab」に学ぶ新規事業の育て方, JAC Recruitment(リンク)
※7:Samsung Will Showcase C-Lab Startups Pioneering AI, IoT, Digital Health and Robotics at CES 2025, Samsungのプレスリリース(リンク)
※8:ENERZAi(リンク)
※9:LabSD(リンク)
※10:Quester(リンク)
※11:Unleashing our Superpower: Ericsson's Bold Bet on Intrapreneurship, Daniel Alexus, Ericsson(リンク)
※12:Ericsson Digital Human SDK, SourceForge(リンク)
※13:Bosch Business Innovations(リンク)
【世界のオープンイノベーションの動向調査やコンサルティングに興味がある方】
世界のオープンイノベーションの動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。
先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら
CONTACT
お問い合わせ・ご相談はこちら