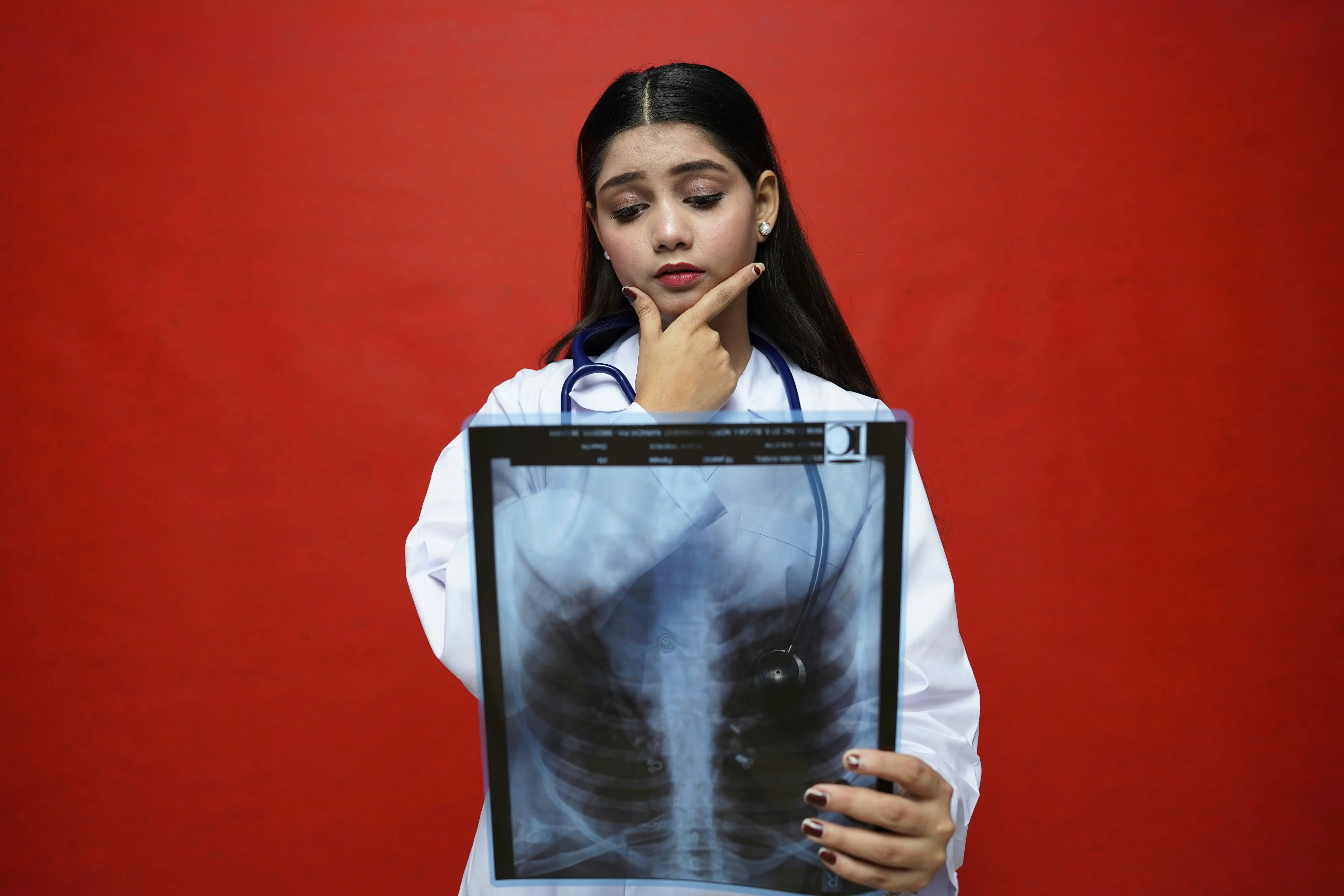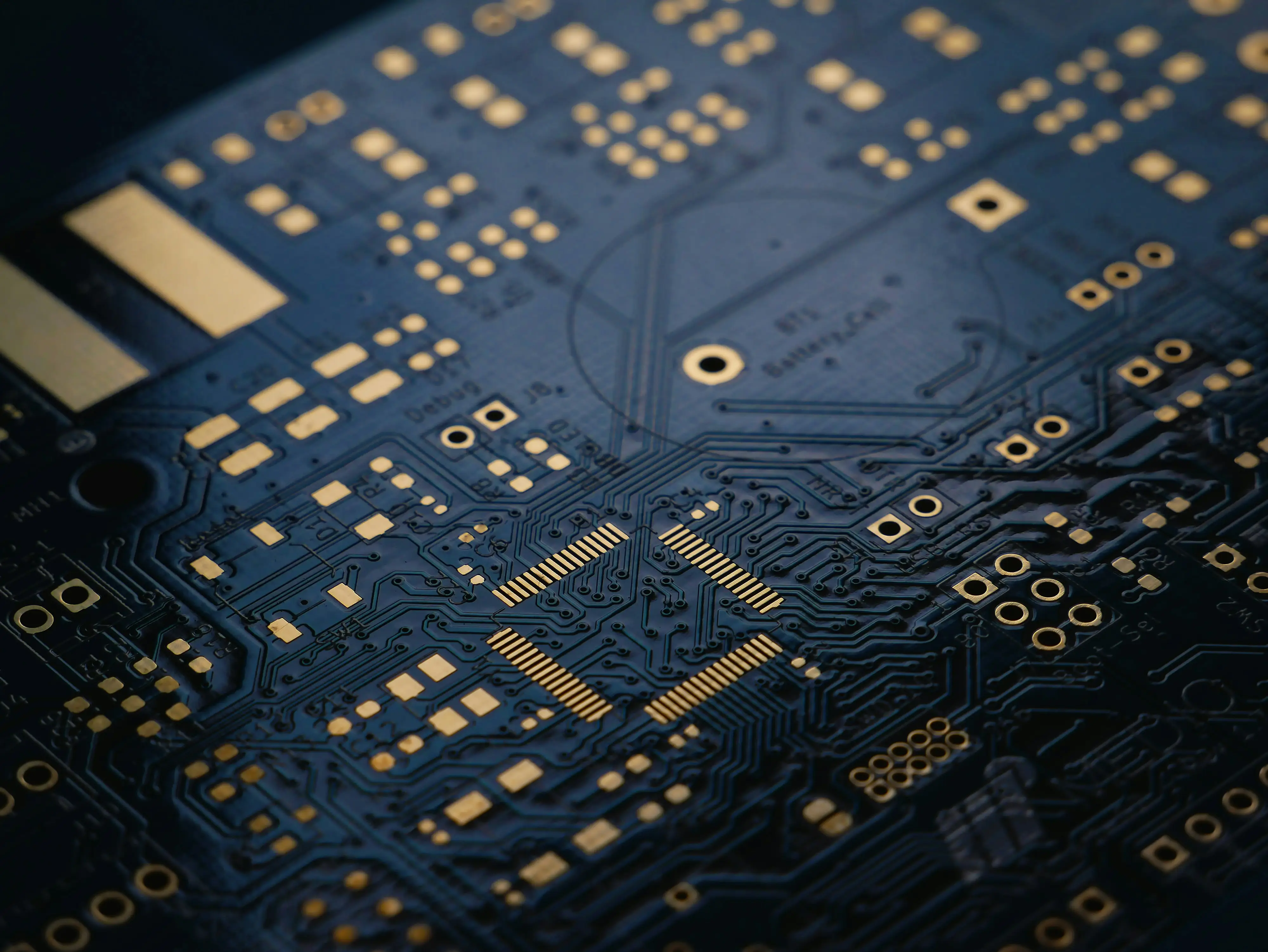ハイブリッドVTOL開発のOdys Aviation、シリーズAで2600万ドル調達

 同社プレスリリースから引用
同社プレスリリースから引用
米Odys Aviationは、ハイブリッド電動垂直離着陸機(VTOL)を開発する次世代航空スタートアップ。独自のフラップ駆動推力制御技術により高効率・長距離飛行を実現し、物流・旅客・防衛などデュアルユース領域での運用を目指す。現在、主力機「Laila」でフルスケール飛行試験を進行中。
2025年10月、同社はシリーズAラウンドで2,600万ドルを調達。リード投資家はNova Thresholdで、Tuchen Venturesや既存株主も参加。資金は米国内での実証飛行、2026年の国際運用開始準備、人員拡充に充当され、開発から商用化段階への移行を加速する計画となっている。
長距離飛行と安全性の両立する次世代VTOLを開発
現在のeVTOL市場では、航続距離の短さや積載制限、騒音・安全基準の厳格化、そして認証制度の複雑さが実用化の障壁となっている。特に都市間や離島輸送、防衛・災害支援など長距離・高信頼運航が求められる領域では、既存電動機体では対応が難しく、技術面と制度面の両立が課題となっている。
同社は、ハイブリッド推進と独自のフラップ推力制御技術を組み合わせ、長距離飛行と安全性を両立させる次世代VTOLを開発。米国でのフルスケール試験と2026年の国際実証運航を通じ、認証取得や標準化を推進する。政府・航空会社との連携により運用体制を整備し、空のモビリティ実装の実現を目指している。
ハイブリッド推進とフラップ制御による次世代長距離VTOL設計
同社は、電動モーターと内燃エンジンを組み合わせたハイブリッド推進システムを採用し、電動機のみでは限界となる航続距離と積載性能を補っている。これにより数百マイル級の中距離飛行が可能となり、発電と推進を分離した効率的な設計で信頼性を高め、物流・防衛・旅客輸送など幅広い用途に対応することを目指している。
機体制御には、ティルトローター方式に代わる独自の“flap-based thrust vectoring(フラップ駆動推力制御)”を導入。翼面フラップの角度を変えて推力方向を調整する仕組みで、構造の簡素化と軽量化を実現した。これにより整備性や安全性が向上し、冗長設計によって故障リスクを最小限に抑えつつ安定した垂直離着陸を可能にしている。
さらに、低騒音・高冗長性・モジュール化を重視した機体構造を採用し、都市部での運航にも適した静粛性を確保。AIを活用した自律制御や障害回避システムも統合し、安全性と運航効率を両立している。JARUS/SORA準拠の設計を進め、FAAやEASA認証取得を見据えた開発を推進。現在は主力機「Laila」のフルスケール試験が進行しており、大型モデル「Alta」への展開も予定されている。
長距離VTOLによる持続可能な航空インフラの確立を目指す
CEOのJames Dorris氏は「今回のシリーズAはOdysにとって技術実証から実運用への転換点となる」と述べ、次段階では“Laila”のフルスケール試験を通じて性能・安全性を実証し、商業化準備を加速すると語った。また「長距離・高効率・低コストという現実的な航空モビリティを実現することが、私たちの使命だ」と強調している。
VPのAndy Apple氏は、「我々は単なる航空機メーカーではなく、AAM(先進航空モビリティ)の運用エコシステムそのものを構築する企業だ」と述べ、規制、インフラ、運航、整備を含めた包括的枠組みを国際的に整備していく姿勢を示した。投資主導のNova ThresholdのJustin Hamilton氏も「Odysは防衛や貨物輸送など最も現実的な領域から市場投入を進める」と評価している。
同社は2026年の国際実証運航を皮切りに、型式認証取得と商用展開を並行して進める計画だ。オマーンや米国を中心にAAM運用拠点の整備を進め、政府・航空会社との連携を強化。さらに大型機「Alta」開発や完全電動化への移行も視野に、長距離VTOLによる持続可能な航空インフラの確立を目指している。
参考文献:
※1:Odys Aviation Secures Series A Funding to Accelerate Full-Scale Flight Testing and Global Operational Launches( リンク)
※2:同社公式HP(リンク)
【世界のエアモビリティの技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】
世界のエアモビリティの技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。
先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら
CONTACT
お問い合わせ・ご相談はこちら